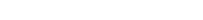学園南地域自治協議会規約(令和6年4月14日改正)
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、学園南地域自治協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、学園南地区を住みよい地域にするため、学園南地区自治計画に基づき地域一体となって民主的に地域づくりの実践に努めることを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 協議会の事務所は奈良市学園南三丁目1番3号近鉄学園前駅南口西部再開発ビル南棟1階集会室に置く。
(対象領域)
第4条 協議会の対象領域は学園南区域(別表1参照)とする。
(取り組み)
第5条 協議会は第2条の目的を達成するため、次に掲げる取り組みを行う。
(1)地域の課題の把握や情報の発信
(2)地域の課題解決に向けての協議及び事業の実施
(3)「地域自治計画」に基づく事業の実施
(4)その他、本会の目的達成のために必要な活動
2 協議会は第7条に定める構成員が、組織の運営及び活動に参加しないことを理由として、不利益な取り扱いはしないものとする。
(活動の制限)
第6条 協議会は宗教活動、政治活動、および営利活動は行わない。ただし、協議会の構成員の利益収受を伴わない協議会自身による営利活動を行うときは、第13条に定める総会の議決を得るものとする。
第2章 協議会の構成
(協議会の構成員)
第7条 協議会は次の各号に掲げるものとする。
(1)協議会の区域内に居住する全ての者
(2)次に掲げるもののうち、協議会への参加を希望し、第24条に定める理事会が承認したもの
(ア)区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(イ)区域内で活動する個人及び法人その他の団体
(ウ)区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(エ)区域内に存する学校等に在学等する者
(3)前号の規定のかかわらず、暴力団及び暴力団若しくはその構成員の統制下にあるもの、並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する処分を受けている団体又はその統制下にあるものは協議会の構成員となることができない。
第3章 役員
(役員)
第8条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 3名 (3)書記 1名 (4)会計 1名 (5)監事 2名以内
(役員の選任)
第9条 会長は総会において、会員の中から選任する。選任手続きは別に定める。
2 選任手続きは、別に定める「役員等選考委員会規程」により定めることとする。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、協議会を代表し、会務を統括するとともに学園南地区連合会長を兼任する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)書記は、事務的業務を統括する。
(4)会計は、協議会の会計事務を行う。
(5)監事は、協議会の会計、資産及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告をする。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は次のとおりとする。
(1)会長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(2)その他の役員の任期は1年とし、定例総会の終了の時を以て当該年度の任を終えることとする。ただし再任は妨げない。
(3)役員の中で欠員が生じたときには、第9条及び第16条の定めるところに拘わらず第24条に定める理事会の承認により役員の補充を行うことができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会議
(会議)
第12条 協議会の会議は、総会、理事会、部会及び委員会とする。
2 会議は、原則全て公開とし、協議会の構成員は傍聴できるものとする。ただし、それぞれの会議を代表する者が認めた場合はその他の者も傍聴できるものとする。
第5章 総会
(総会)
第13条 総会は、協議会の最高議決機関とする。
(総会の種別)
第14条 総会は、定期総会と臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第15条 総会は、代議員をもって構成する。
2 代議員は46名までとし、別表2に掲げる各団体より選出した者と公募により選ばれた住民で構成し、任期は1年(翌年の定期総会の終了まで)とする。ただし、再任は妨げない。
3 公募住民の定数は3名までとし、定数を超えた応募があった場合は抽選とする。
4 代議員の資格要件は、第7条に定めた協議会の構成員であること。
(総会の権能)
第16条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算案
(2)事業報告及び決算
(3)地域自治計画の変更
(4)規約の変更
(5)総会で提案された事項
(6)役員の選任と解任
(7)その他協議会の運営に関する重要な事項
(総会の開催)
第17条 定期総会は、毎年度決算終了後1ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めた場合又は代議員の3分の1以上の請求があった場合に開催する。
(総会の招集)
第18条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、少なくとも会議を開く1週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、代議員に通知を発しなければならない。また、所定の場所に掲示しなければならない。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、その総会に出席している代議員の中から互選により選出する。
(総会の定足数)
第20条 総会は、代議員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(総会の議事及び議決)
第21条 総会の議事は十分に話し合い決する。意見が分かれた場合は、出席代議員の過半数を
もって決し、可否同数となった場合は議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第22条 やむをえない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項に
ついて、議長又は他の代議員を代理人とし、委任状により表決を委任することができる。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。
(1)日時及び場所、代議員総数及び出席代議員数(委任状を含む)
(2)審議事項及び議決事項
(3)議事の経過の概要及びその結果
(4)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 理事会
(理事会)
第24条 協議会の運営に関する事項及び総会に諮るべき事項を審議決定するため、理事会を設置する。
(理事会の構成)
第25条 理事会は部会長及び自治会長、別表2に掲げた各団体からの理事をもって構成する。
2 理事には別に公募選出の住民1名を加えるものとし、その任期は1年(翌年の定期総会の終了まで)とする。ただし、再任は妨げない。
3 理事は、代議員を兼ねることができる。
第26条 理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会で承認を得た事業計画に基づく事業の実施に関する事項
(3)規約に定める事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の招集)
第27条 理事会は、会長が招集する。
(理事会の議長)
第28条 理事会の議長は会長が務める。ただし、会長に事故があり出席出来ない場合、会長が指名する副会長が代理できるものとする。
(理事以外の出席)
第29条 会長が必要と認めるときは、理事以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(理事会の定足数)
第30条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議決)
第31条 理事会の議事は十分に話し合いの上決する。意見が分かれた場合は出席理事の過半数をもって決し、可否同数となった場合は議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第32条 理事会の議事録を作成し、次の事項を記載する。
(1)日時及び場所、出席理事数及び氏名
(2)審議事項及び議決事項
第7章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
第33条 事業計画に基づく事業を実施するため3部会を設置する。また理事会の承認の上委員会を設置することができる。
2 部会及び委員会の長は、部会及び委員会を構成する者の中から互選により選出する。
(1)自治・教育に関する部会
(2)防災・防犯に関する部会
(3)福祉・交流に関する部会
(4)その他・会長が要請した事業の推進並びに課題案件諮問の為の委員会
(部会及び委員会の報告)
第34条 部会長及び委員長は、理事会に対し、事業の執行状況を報告することとする。
第8章 事務局
(事務局)
第35条 協議会の円滑な運営を行うため、事務局を設置することができる。
2 事務局には事務局長を置き、理事会が選任する。
3 事務局の運営に関する事項は、事務局長が会長の指示の下統括する。
第9章 地域自治計画
(地域自治計画の見直し)
第36条 地域の将来像、目標、基本方針等をまとめた地域自治計画について、適宜検討し、必要に応じて見直すものとする。
第10章 会計及び監査
(収入の構成)
第37条 協議会の経費は、協賛金、協議会が行う事業等の収入、市からの交付金及びその他の収入を以て充てるものとする。
(会計年度)
第38条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計帳簿の整備)
第39条 協議会は、会の収入、支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。
2 構成員による帳簿閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、この閲覧を認めなければならない。
第11章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第40条 この規約を変更する場合は第21条に関わらず総会において、代議員の過半数以上の賛成を得なければならない。
(解散)
第41条 協議会を解散する場合は、第21条に関わらず、総会において、代議員の4分の3以上の賛成を得なければならない。
第12章 その他
(その他)
第42条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規約は、令和元年6月1日より施行する。
この規約は、令和6年4月14日から改正、施行する。
別表1 (第4条関係)
| 協議会の区域 | 町名一覧 |
|---|---|
| 学園南一丁目、 学園南二丁目、 学園南三丁目、 学園大和町一丁目の一部 |
別表2 (第15条関係)
※代議員・理事の定数は目途とする。
| 地区内構成団体 | 代議員数 | 理事数 |
|---|---|---|
| 学園南地区自治連合会 | 2 | 2 |
| 一丁目自治会(2自治会) | 2 | 2 |
| 二丁目自治会(3自治会) | 3 | 3 |
| 三丁目自治会(4自治会) | 4 | 4 |
| 学園南地区自主防災・防犯協議会(9防災・防犯会) | 4 | 1 |
| 学園南地区地域安全推進委員会、交通安全指導員会 | 6 | 1 |
| 学園南地区社会福祉協議会(福祉部会) | 6 | 1 |
| 学園南地区民生・児童委員協議会 | 7 | 1 |
| 学園南いきいき子ども会 | 1 | 0 |
| 富雄南中学校区少年指導協議会 | 1 | 0 |
| 学園南地区スポーツ推進委員 | 1 | 0 |
| あやめ池小学校、学園南こども園、帝塚山学園各PTA | 1 | 0 |
| NPO法人奈良シニアIT振興会 | 1 | 0 |
| 学園前街育プロジェクト実行委員会 | 2 | 1 |
| 富雄東包括支援センター | 1 | 0 |
| 公募による住民 | 2 | 1 |
| 計 | 44 | 17 |
学園南地域自治協議会役員等選考委員会規程
(名称)
第1条 この会は役員等選考委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この規程は学園南地域自治協議会規約第9条に基づく役員の選任について定めるとともに、広く地域自治協議会活動のための人材を発掘し優れた指導者を選出するための委員会運営に関し必要な事項を定め、民主的かつ公平な方法で選出されることを目的とする。
(選出対象者)
第3条 委員会の行う選出の対象者は次のとおりとするが、副会長以外の役員は会長が推薦し、総会の承認を得る。
(1)学園南地域自治協議会 役員
会長(連合会長兼任)
副会長
書記
会計
監事
(2)その他自治協議会等地域の発展のために地域自治会長が必要と認めた者。
(役員の選出方法)
第4条 前条第1号の役員については、総会において出席者の過半数の承認を経なければならない。
(委員長及び委員)
第5条 委員会の委員長は、委員の互選により選任する。
2 委員会の副委員長は、地域自治協議会副会長及び監事が就任する。
3 委員会は10名以内で組織し、委員長が選任する。
4 委員の任期は必要な選出対象者全員が、新たな役職に就任したときまでとする。
(委員会の職務)
第6条 委員会は、会長候補者の選出に関する次の事務を行う。
(1)会長選挙の公示
(2)立候補者の届出受理及び審査
(3)立候補者名簿の公表
(4)選挙結果の確認と発表
(5)その他の必要な事項
(選出の時期)
第7条 委員会の発足は、新役員等の就任年度の前年概ね1月初旬とし、選出の期日は3月末までに内定するよう努める。
(選出の留意事項)
第8条 対象者の選出は、原則地域内居住者とし自治会経験者等を考慮し決定する。
2 特定した者に負担が集中しないよう広い範囲から人材を発掘する。
3 組織活動引継ぎが円滑となるよう再任について配慮する。
4 組織活性化のため、若年層や女性を積極的に参加させる。
5 特定の委員に選出を一任することのないよう委員全員で調整し決定する。
(会長候補者の資格)
第9条 会長候補者は、下記要件を全て充足することを要する。
①学園南地区居住者であること
②自治会会員であること
③地域自治協議会役員経験者であること
2 候補者は自薦、他薦を問わないこととする。
(その他)
第10条 上記規程で定めのない事項は、地域自治協議会の理事会にて決定することとする。
(附則) 本規程は令和6年4月14日より制定、実施する。